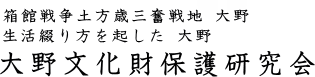父(推奨)
大野小高二 若松 きよ
大正六年の九月、私が九つの時、父は汽車に轢(ひ)かれて死んだのでした。その時分は山にいて炭を焼いておったが、節句(重陽(ちょうよう)の節句)に帰って来て餅(もち)を沢山(たくさん)持ってまた山に行く時、停車場(駅)の前の店に寄って、酒を飲んで酔った機嫌(きげん)で線路に行って轢かれたのだそうです。
私が五つの時、父はある事情で私の家を出たのでしたが、その晩はなんだか淋(さぴ)しい晩で、母は「おらの背中を、何だかおぶさっていたようだ」と言いながら、背中をさぐっていた。私と兄とは母の顔ばかり見ていた。垣が、がさがさすると誰か立.っているのではないかと、窓から外ばかり見ていた。母は「何だか淋しい晩だなあ。寝るべし、寝るべし」と言って早く寝た。少したつと「寝たがね、寝たがね」と戸を叩く音がしたから、私は母を起こすと、母はむっくり起きて「はい」と言って片手をつき、頭を上けたきり耳をすましていると、這入(はい)って来たのは父の祖母でした。いきなり母に「あの五郎、死んだって知らせ来たもんだ」と声をふるわせながら言って、上がり掛けに腰を掛けて、すくすく泣き出した。母ぱ驚いて「あん」と思わず叫(さけ)んで起きた。
それで私も兄も起きて、四人で父の家へ行って見ると、父の着てあった着物や白い手拭(てぬぐ)い三尺(三尺手拭い)などが、血のついたまま床板の上に投げてあった。母は私と兄の手をぎっしり両方に引いて行こうとしたら、兄は「おれだっけぁ見たくねぇでぁ(俺は見たくない)」と泣きながら手を振った。私もおっかなくなって泣いた。親類の人達は「見ねつの見せて気悪くすれば悪いして、かもねでおかせ(見たくないと言うのに見せて具合を悪くするといけないから、ほっておきなさい)」と言った。それでも、私は母と二人で奥に行った。棺桶(かんおけ)はもう縄を掛けられて、あたりには花が並べてあった。縄をとき、蓋を取ったら白い包帯で頭を包んだ父は、何とも言われない程(ほど)、物凄(ものすご)く座っている。母は「うん、こんな死に方しねがら死なれねもんだがな(こんな死に方でなければ死ねないものだろうか)」と言いながら、父の包帯した頭を夢中でばんと叩(たた)いて泣いた。
葬式の日、母も私も白い着物を着て、私に一膳飯(いちぜんめし)を持たせ、自分は金.の花を持って行った。前の方で小さい鐘が、広い野原の中に、カンカンカンと静かに鳴って行った。焼き場(火葬場)に行って、台の上に棺桶を上げて、薪を立てた。杉葉や薪に火がついて、煙が.出た時、母は「もう帰るんだ」と言って、私の手を引いた。後ろを見ると、杉林の問から、煙がもうもうと上がっていた。
大正14年3月号
■ことばの意味
【大野小高二】大野尋常高等小学校高等科二年。当時は尋常科六年、高等科二年で、今の中二。
【上がり掛け】入り口(玄関)の土間から居間へ上がる段差。
【三尺手拭い】鯨尺(くじらじゃく)(和裁用の物差し)で長さ三尺(約114センチ)ほどの木綿(もめん)の手拭い。
【一膳飯】死者に供える盛り切りの著を立てた飯。
※漢字や仮名遣いは現代風に改めています。方言などわかりにくい表現は、かっこ書きで補足しました。
■綴方選評 鈴木三重吉
年級としては写象(しゃしょう)の把握が少し簡単すぎますが、叙写(じょしゃ)が純朴な上に、描き方が簡潔に印象的にまとめ上げられているため、ド手な精密さを持って記述された作よりもずっと自然な感銘が受けとれます。お母さんが「何だか淋しい晩だなあ。寝るべし、寝るべし」と言われるあたりや、むっくり頭を上げ、片手をついて.耳をすまして聞かれる前後や、お父さんが亡くなられたと聞いて、立ち上がられたところや、お父さんの死体の頭を叩いて泣かれるあたりなどは、よく活写的に描けています。葬式の日に、野原にさびしく響く鐘の音に涙をのみのみ行くところや、杉林の中から火葬の煙が上がるのを見て帰ってくるところなどは、簡単な叙写の中にしみじみした悲哀がこもっています。若松さんの学校は木村校長が熱心な綴方研究家で、氏の努力で全校の年級がそろって私の希望どおりに引き上げられて行くので、私としても愉快(ゆかい)でたまりません。