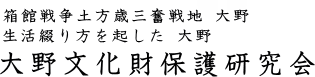焼場(やきば)の爺さん(賞)
大野小高二 金川 つわ
二、三年前の正月近くであった。私が学校から帰ると、母が私に「これ、広島さんとこさ、くれて来い」と、元日の朝食う餅と米とをよこした。広島さんというのは、腰の曲(ま)がった、七十ばかりの親類も兄弟もない、可哀そうな爺さんです。父が生きていたとき永(なが)く使った人で、広島県から来たというので、広島さんと呼ぶのです。
家では父が死んで、田を作ることをやめてから、人を使うくらい忙しくもないので、暇をくれてやった。が、家から出て行っても入る家がないので、近所の人たち四、五人で田圃(たんぼ)の傍(そば)の寺の焼場(火葬場)の所に、竹や柴(雑木)で小屋を建ててくれた。家ではその時、鍋や釜、金盥(かなだらい)_(金物製の平たいおけ_)、蓆(むしろ)(わらなどを編んだ敷物)、父が畑に出るとき着たどんじゃなどをくれてやったが、爺さんは、そこに一人で暮らしていた。
私は一人で行くのが淋しいので困っていると、そこへ照ちゃんがきたので、「照ちゃん、広島さんところさ、かだってあべ(一緒に行こう)と言うと、照ちゃんが薄笑いしながら「あの小屋さげ」と言って、二人で堅雪(かたゆき)の上を話しながら行った。爺さんの小屋の前に行ってみると、ぼろぼろに切れた蓆が戸口(とぐち)に下がってあった。私は恐る恐る蓆を上げて見ると、中に誰もいない。ただ、戸口の前に、金盥に雪を沢山入れて手で押したように、かたがついていた。炉(囲炉裏(いろり))には空鍋(からなべ)が一尺(約三十センチ)も高く掛けてあった。
いくら見ても爺さんがいないので帰ろうとすると、照ちゃんが「あれ、いださ」と言ったので、よくよく見ると、今まで私に見えなかったが、正面に、切れたどんじゃを一枚掛けて、その下から紫に張り切った太い脛が二本出ていた。私たちは眠っていると思い、声を高く「広島さん、広島さん」と呼んだが、起きない。また「広島さん、火事だ、火事だ」と言っても返事がない。そこで死んでいるのではないだろうかと思うと、急に恐ろしくなって、二人で戸口の蓆を掛けずに飛ぶように走って家に来て、母に話すと、母はたまげて「凍(こご)え死んだんでなかべか(ないだろうか)」と言ったが、その話はすぐ隣近所に知れ、子供や大人が沢山小屋の方に走って行く。私はあまりの恐ろしさに、二度と見るに行く力がなかった。
それからしばらくたって、また照ちゃんと二人で行って見ると、さっきまであった小屋は、もう焼かれて灰になり、少し煙が出ていた。そしてすぐ脇に、爺さんは白い箱に入れられ、穴に埋められるところであった。まもなく土をかぶせられ、その上に仏板(ほとけいた)(木製の墓標)を立てた。そして向かいの婆さんが持って来た線香と蝋燭(ろうそく)を灯(とも)して、うるかした米(水に浸した米)をその上にまいた。
そのうちに坊さんが数珠を掛けて、小さい鈴を鳴らしながら、お経を上げ始めた。あたりはしィんとしている。その時の恐ろしいほどの淋しさは、今も忘れない。
大正13年9月号
■綴方選評 鈴木三重吉
応募総数千二編の中から二十編だけ予選し審査しました。高等二年の金川さんの「焼場の爺さん」は、第一に、材料として非常に珍しい驚異的なものです。下手な大人の作家たちが事象に深刻味を加えようとして、わざわざ強調したりするような叙写と違って、ありのままを、言わばただただ無雑作に、素直に記述している、その純朴さと真実性とのために、事実が独りでに感銘強く胸に迫って来ます。小屋の中に空っぽの鍋をつり下げて、厳寒中に儒絆(じゅばん)一つで凍え死んで、紫色にむくんだ足を出して硬くなっている有様や、しばらく後に行ってみると、もう小屋そのものも焼き払われて、棺桶だけが横たわっているところなぞは、本当にぞくりとするほどの悲惨さです。人間のどん底の生活の証券として、ロシアなぞの陰惨な短編作を読むような気がします。
■ことばの意味
【どんじゃ】労働着。刺し子。綿布を重ね合わせて一針抜きに細かく刺し縫いしたもの。
※漢字や仮名遣いは現代風に改めています。